高校生の時に会社を作って潰したことがある。今思えば向こう見ずの極みといえるような無謀な行動だったので結果が失敗に終わったのは当たり前だと思っているが、実際に起業して会社を経営し学んだこと、実際にやったからこそ気づいたことはたくさんあった。
これは、実際に起業で失敗を繰り返した先行者である筆者が、実体験で綴る備忘録だ。起業するときにやってはいけないこと、陥りがちな失敗を、創業計画時、開業時(※実際に開業するとき、会社を設立するとき)、起業後に分けたうえで、挙げられるだけ挙げている。
この記事には、実績ある起業家が語るきらびやかなサクセスストーリーや、専門家が語る高度な経営のコツは書かれていない。しかし、実務ベースで役に立つ情報はたくさん載っていると自負している。情熱や希望を抱いている人に冷や水を浴びせるような内容であることは自覚しているが、浮かれすぎずに冷静になるための薬として読んでもらえれば幸いだ。
これから起業する人や、起業を考える人が筆者と同じ轍を踏まないことを祈る。
創業計画時にやってはいけない失敗と取るべき行動

起業するという人が何も考えずに、準備もせずにいきなり開業することはないだろう。しかし、この下準備の段階である、事業計画書の作成をはじめとした創業計画を立てる段階で、既に落とし穴は存在している。これを回避することがまず大切だ。
起業後のキラキラした人生を考えている時、人はどこまでも向こう見ずになれるが、一旦これを読んで冷静に考えてほしい。
1.かっこいい事業よりできることで確実に稼げることから始める|金が尽きればゲームオーバー

今の世の中は貨幣経済で成り立っているわけだが、そのような社会で事業を営むルールはシンプルだ。(やれば捕まって経営を続けられないので)法律を守ったうえで、キャッシュが尽きればゲームオーバー、大儲けしなくても資金ショートにならなければ少なくとも継続はできる。
つまり、「少なくとも負けないことが大切」ということになる。
よって、どんな目的であれ、金を稼ぐために起業して事業を始めるなら、泥臭い仕事だろうが、自分にできることで、確実にお金が稼げる仕事から始めることが最善手だ。
例を挙げると、ITやWEBの業界で起業するなら、自社プロダクトのみに注力するのではなく、受託開発などの下請け仕事も並行して実施する事で最低限会社が存続できるだけの収入源を確保することは一般的である。また、(一昔前の話だが)、同業界にはキュレーションメディアや資料請求サイトのような、やればとりあえずお金が入る可能性が高く稼ぎやすい鉄板のビジネスのようなものもあった。
起業に夢を見ている人ほど、全く新しい技術や斬新なアイデアに基づく、メディア受けするようなキラキラした雰囲気の事業を夢見がちだ。しかし、そんな事業で成功している人や会社は世間全体から見れば一握りである。まずは、存続する事、そのために泥臭い事業で金を稼ぐことを考えよう。
2.副業や週末起業から始めて事業が軌道に乗ってから会社を辞める

いきなり会社を辞めて安定収入を無くすのではなく、副業などの週末起業から事業を始め、勤め人の収入を上回るなどして十分に食っていけるようになった段階で会社を辞めることも有効な選択肢だ。この理由は2つある。
まず、副業や週末起業から始めていれば、仮に事業が黒字化しなくても食えなくなることがない。資金ショートの心配を減らせるのは大きなメリットだ。事業がうまくいかなくなった時に、ピポッドして継続することがしやすくなるし、黒字化する前の先行投資の期間で力尽きることも避けられる。また、起業を諦めて会社員に戻ることも容易に行える。
次に、これが最大のメリットなのだが、実際に事業をやることで自分が起業して始める事業に情熱を注げるかを確認することができる。
副業を継続するモチベーションが続かないという話は往々にして聞くが、起業経験があるものとして、副業ですらモチベーションが続かない事業を本業にしたところでモチベーションが増えることは無いと断言できる。事業が常に順調なことは考えにくい。よって、起業する人には、辛い時でも仕事を投げ出さない強い意志が必要なわけだが、追い詰められることでやる気を無くす人は普通にいるし、それは責められることでもない。
起業する意思を固めたのであれば、失敗しても収入が下がらないというメリットを享受するため、副業の規模から始めてみるのはおすすめだ。そして、もし、副業で起業した後、ピンチの時やうまくいかない時に事業への情熱を失うようなことがあれば、そもそもあなたは独立すべきではないと言えるだろう。
筆者が起業したのは高校生の時であり、(通信制高校なので週5日以下ではあるが)毎週学校に通いながら会社を経営していたので、週末起業として始める起業を実際に実践していた。
親に養ってもらえる子供の頃の話で普通に実家で暮らしていたことから、社会人として自立していかないといけない状態で起業する人とはプレッシャーが違うと言えばそれまでだ。しかし、少なくとも学校は辞めず、大学に進んで就職するレールから下りない状態を維持していたので、プレッシャーは感じつつも極端に追い詰められる感覚を味わうことはなかった。
そして、右肩上がりに成長しない状況が続いてモチベーションが尽きたことで会社経営の継続を諦め、現在は大学を出て普通に就職している(そして、学生時代の仲間と当サイトを運営するなど、ちょっとした事業や投資にいくつも手を出している)。
3.なるべく個人事業主から始める|法人は維持費が高く撤退も手間

先述した副業や週末起業といったスモールスタートに通ずる話だが、起業するなら個人事業主から始めることを強くお勧めしたい。これは固定費の削減と、起業が失敗に終わった万が一の時の撤退を考える視点からの意見である。
個人事業主は開業届一枚でなることができるのでコストがほぼかからないし、副業程度では開業届を出さないことも選べる。これに対して、法人は資本金に加えて設立費用も発生することから、初期費用がかさみやすい。
また、個人事業主の毎年の決算は確定申告で事足りるが、法人は素人が自分でやるのは困難な決算申告が必要であり、毎年税理士を雇うお金がかかる。また、法人は法人税の均等割によって赤字でも最低数万円は税金を取られるため、維持費の観点でも起業初期にはデメリットが大きい。
加えて、法人は撤退も面倒だ。個人事業主は廃業届一枚で辞められるが、会社を畳むとなると手続きが煩雑で司法書士等の専門家を雇う必要に迫られるほか、官報への情報掲載などの費用も取られる。廃業時はただでさえ金回りが厳しいと想定されるため、これは無視できないリスクとなる。
もちろん、法人には信用が生まれることや、出資を受けやすいこと、有限責任で出資額以上の責任を負わなくてよいという法的な保護を得られる等のメリットがある。ただし、日本は借入時に代表者の連帯保証を求められることが一般的なので、リスク回避の観点から一番のメリットといえる有限責任の恩恵は限定的だ。賠償責任に関しては、フリーランス向けの賠償責任保険があるので法人を選ばなくても対策はできる。
よって、初期から出資を受けたり、信用が非常に重要な業種/事業で起業しないのであれば、無理をして法人を選ぶ必要は無いと言えるだろう。
筆者の場合、起業した時に未成年だったことで行える法律行為に制限があり、経営に支障が出ることからやむなく会社設立を選んだわけだが、個人事業主で始めたかったのが本音だ。
4.会社を作るなら株式会社を選ぶ|合同会社には落とし穴があり無限責任の法人格は論外

一つ手前の項目にて、撤退のしやすさの観点から、起業するなら法人より個人事業主でスモールスタートすることをお勧めした。しかし、様々な理由で最初から会社を設立して法人でスタートするという人もいるだろう。そのような方には同じ撤退のしやすさの観点から、株式会社を選択することを強くお勧めしたい。
会社の経営を停止するときの選択肢として、会社を畳む(=解散)のほか、休眠という選択肢がある。しかし、株式会社には役員の任期があり、定期的に変更登記をして任期を延長させる必要があるが、株式会社がこれをせずに休眠を続けていると、国によって解散させられてしまう「みなし解散」が行われる。
これは恐ろしい制度にも思えるが、特に借金や清算する資産などが無い会社を畳む場合、休眠届だけ出して放置しておけば勝手に会社を畳んでもらえるので、廃業費用を抑えられるというメリットがあるのだ。廃業時の費用は最低でも15万くらいはかかるため、金が無いことが想定される廃業時には無視できないメリットといえる。最初から大風呂敷を広げて出資や借り入れをたくさんする予定の起業家には向かないが、自分の食い扶持を稼ごうとするだけの人にとってはかなりお得だ。
しかし、同じ有限責任の法人格である合同会社にはこのみなし解散の制度が無い(※役員の任期が無いためと言われている)ため、設立費用は安いが畳むのに費用が掛かる。よって、最初に設立費用を多めに支払ってでも、株式会社を選んだほうが良い。また、無限責任の法人形態である合資会社や合名会社は論外だ。
ちなみに、一般社団法人と一般財団法人、役員に任期があることからみなし解散の対象となるため、非営利法人を立ち上げる際はこれらの法人格を選ぶのがおすすめである。
5.自宅を本社にしない|法人の本社はネットに公開されるが代表者宅は登記簿にしか載らない

個人の生活でも一番大きな固定費は大概が家賃であるが、それは起業する場合も同じである。よって、自宅でできる仕事で起業する場合、会社を設立する際に自宅を本社にしようと考える人がいるが、これは絶対に避けるべきだ。
聞いたこともない会社を調べた経験がある方はご存じだと思うが、法人の本社所在地というのはネットで広く公開されている。グーグルマップのような自分で自発的に掲載するサイトではなく、法人の情報を勝手に集めて勝手に掲載しているデータベースのようなサイトがたくさんあるし、なんなら国税庁の法人番号公表サイトという、国営のサイトまである。
しかし、このようなネット上で公開されることが避けられない法人の住所は本社所在地までであり、代表者の自宅住所は掲載されない。よって、営業のDMなどの不要な郵便物の多くは本社にやってくる。履歴事項全部証明書をはじめとした登記簿には元から代表者の自宅が載っていることから、調べようと思えば実際は自宅の住所はわかってしまうのだが、それでもネットで誰でも見れるレベルで公開されないのは大違いだ。
家で仕事ができて、物理的な業務スペースがあるオフィスが要らないという場合には、バーチャルオフィスという選択肢もある(この場合、バーチャルオフィスが提供する郵便の転送サービスをつければ必要な郵便は自宅に届くようにできる)。とにかく、会社を設立するなら自宅を本社にするのは辞めよう。
6.創業時に借入はしない|出資すら集められない事業は成功確率が低い

創業時はついつい借り入れによってまとまった資金を集めたくなるが、正直なところ筆者はおすすめしない。理由は至極単純で、借金だからだ。
確かに、借り入れによって多額の資金を集めないと創業しづらい、初期費用が多く発生する事業もある。よって、創業融資のような起業時の借り入れを完全に否定する気はない。
しかし、リスクを回避しつつ成功を目指すのであれば、多額の初期投資を必要としないスモールスタートで事業を始めることや、革新的な事業であれば出資によって資金調達をすることも検討すべきと考えている。特に、後者のような世の中にない新しい事業の場合、出資すら集められないのでは成功確率は低いと言わざろう得ないだろう。
創業時は借り入れはなるべくしない、借り入れを行う場合でも極力少額に抑えることが重要である。
7.最低1年は生き残れる運転資金を確保しておく|カツカツでの起業は無謀
起業はキャッシュが尽きた時がゲームオーバーの時なので、ビジネスが軌道に乗って安定的に稼げるようになるまでの運転資金は当然必要になる。この運転資金を確保しておく期間は多ければ多いほどよいが、どんな事業で起業するにしても、最低1年分は確保しておきたい。
実は、この「最低1年」という基準に明確な根拠は無い。そもそも、起業して行う事業の種類も、すぐに売り上げが立つことが期待できる、フリーランスとしての受託ビジネスや飲食店をはじめとした実店舗から、市場作りから始める必要があって多額の先行投資が必要となる革新的なアイデアや技術によるものまで様々であるため、言ってしまえば「多いに越したことは無いが、必要な額は結局ケースバイケース」というのが正確な言葉である。
では、なぜすぐに売上が立つ事業を含めて最低1年は必要だと言っているのかというと、起業すると想定外の出費が発生することが珍しくないからだ。例を挙げると、本業に関わる固定費や変動費といった経費だけでなく、関係者の冠婚葬祭の発生、急遽必要になる機材等の調達や外注費の発生などで、当初の想定通りに売上が伸びたとしても資金繰りの余裕が失われることが十分に考えられる。
筆者の場合、学生でお金を持っていなかったのでやむなく少ない運転資金で事業を始めたのだが、例えば、当初の計画に無かったアフィリエイト広告の出稿を決めた際に、自社サービスのサイトにやや複雑なプログラムの追加が発生し、急遽エンジニアにサイトの改修を依頼するといった急な出費があった。筆者の場合は受託でも稼げたので何とかなったが、そうでなければ即刻倒産していたであろう。
運転資金はなるべく多く用意するのが懸命だ。
8.固定費はギリギリまで削る|経営はとにかく出費が多い

しつこいようだが、独立起業は資金ショートでゲームオーバーとなる。そして、この資金ショートを防ぐためには売上を上げるだけでなく出費を減らすコスト削減も重要なわけだが、経験上、経営は本当に出費が多い。
よって、まず固定費はギリギリまで削ることを意識して計画を立てるべきだ。
なお、後ほど実際に起業した後にやってはいけないこととして「経費を使って経営している気になってはいけない」という話をするが、起業すると、売上を少しでも伸ばし利益を得ることに固執するあまり、設備にITツールなどあらゆるものを導入したくなり、「投資貧乏」に陥ることがある。また、一国一城の主になったことで気が大きくなり、高級素材を使った高価な法人印やらステータス性のあるクレカやらと見栄による出費を増やすこともやらかしがちだ。
しかし、出ていくお金を増やすことは倒産の確立を増やすことに直結する。もちろん、経営において必要な投資はすべきだが見極めが重要だし、経営者になるなら、あらゆるコストをなるべく安く済ませる方法を考える癖を持つことも大切だ。とにかく、固定費は可能な限り削っておこう。
9.マーケティングと集客の戦略を考えておく|良いものが自然に売れるのは幻想

起業のハウツー本やらマーケティング本やらで聞き飽きるほど言われていることだが、良いものが自然に売れるという考えは幻想である。自分のアイデアに酔いしれる愚かな起業家たちは往々にしてこれを忘れ、「このサービスは革新的だからリリースすればバズってメディアにも取り上げられて自然とユーザーが集まる」とか「うちの店は味には自信があるから、知り合いはみんな来てくれるし、紹介で人が集まってリピーターも生まれる」みたいな根拠ゼロの皮算用をやったりするが、マーケティングや集客の戦略は徹底的に練っておくべきだ。ここから逃げてはいけない。
基本的に考えるべきこととしては、最初に自身の商材のターゲットとペルソナを設定しよう。そのうえで、広告媒体ごとの特徴を勉強し、ペルソナや予算を勘案してどのチャネル(※集客手段)を使って、それぞれどれくらいのコストをかけるかを考えておくべきである。
使用するチャネルは業種との相性があるため一概には言えないが、WEB広告は基本的な媒体であるリスティング広告(Google/Yahoo!など)、ディスプレイ広告(GDN/YDAなど)、アフィリエイト広告の3つを、リアルの広告や集客手段であれば、チラシの配布は最低限検討しておくべきだろう。なお、飲食店や美容室といったポータルサイトがある業種の場合は、ポータルサイトへの掲載も主要なチャネルになりうる。
マーケティングや集客は自分で勉強して極めるのが理想であるが、そこまでできなくても、広告媒体ごとの特徴を最低限把握し、自力でチャネルを選定できるようになるのが良いだろう。
また、起業家や経営者を狙ってマーケティングの支援や代行を行うコンサル業者が群がってくるというのもよくある話だがこれには要注意である。コンサルに依存してしまうと、自分に知見が蓄積されないことで、コンサルなしでは全く集客できずコストばかりがかかる事態に陥りがちだ。加えて、国家資格などがなく実績以外に実力を測る指標が無いマーケティングコンサルは玉石混合の世界のため、口がうまいだけで腕が悪いコンサルに当たってしまうと、コストがかかるのに加えて結果が伴わないという最悪の事態に陥ることもある。
マーケティングや集客は自分で考えるようにしよう。
10.広告宣伝費はなるべく多く確保しておく|集客には試行錯誤の余地が必要
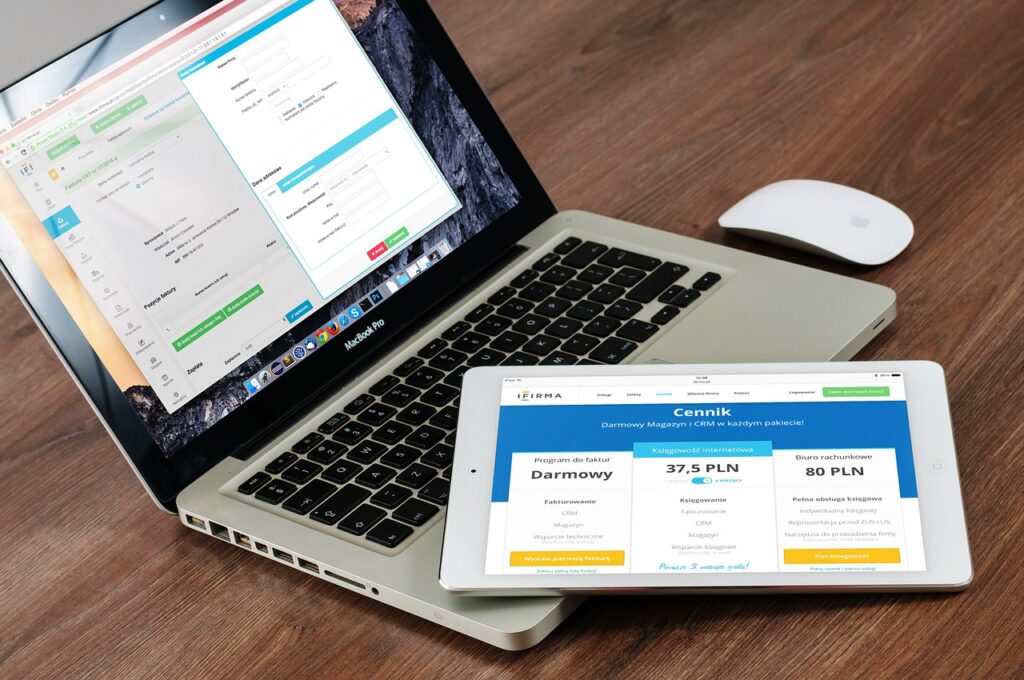
前項でマーケティングや集客の戦略を立てる必要性と、集客はなるべく自力で行うべきであることを述べさせてもらった。この件に関してもう一つ忘れないでほしいのが、起業した後の集客に使う広告宣伝費はどれだけ多くてもよいので、率先してお金を割り振ってなるべく多く確保しておくべきであるということである。
適している広告媒体は業種によって異なり、媒体によって費用も異なることから必要な費用は一概に言えないが、広告宣伝に発生する主な費用として以下の3つのコストを最低限考えておくべきである。
広告宣伝の3大コスト
- 広告の運用費用:広告の掲載や配信等にて発生するランニングコスト
- 広告の制作費用:チラシ/バナー/動画などの制作費用
- 広告の設定費用:WEB広告で必要なコンバージョンタグや計測タグの埋め込みを外注する費用
一番重要なのは広告の運用費用だ。前述のとおり必要なコストはケースバイケースだが、リスティング広告をはじめとした低コストなWEB広告のみを運用する場合であっても最低月5万円は確保しておきたい。WEB広告は特にだが、マーケティングや集客は、施策を実施した後、結果を見ながら改善を繰り返す試行錯誤が重要となる。よって、予算が少なすぎると試行錯誤する余地がなくなり、成果に結びつかない可能性が高いのだ。
また、広告の制作はCanvaといった無料から使えるデザインツールを使って自作することも可能なのでコスト削減の意識は忘れないでほしい。ただし、有料の画像素材を購入したり、プロに写真を撮ってもらったりといった外注費用をかけるべきケースもある。
なお、広告の設定費用として発生しがちである、コンバージョンタグをはじめとしたWEB広告に関連するタグの埋め込み作業は、プログラミングの専門知識を持たない場合は高確率でコストが発生すると考えておくべきだ(アフィリエイト広告は特に複雑なので必須になりがちである)。通常、クラウドワークスのようなクラウドソーシングサービスにて単発の依頼を発注すれば事足りる。
ちなみに、WordPressのようなCMSや、Wixといったホームページ制作サービスやBASEのようなネットショップ作成サービスといったノーコードのツールを使っている場合は広告タグの埋め込みを簡単に行える場合もある。よって、ホームページや自社のECを作る場合は集客機能も考慮してツールを選ぶべきといえる。
総じて、節約するところとお金を賭けるべきところを見極めることが重要である。
11.自分のメディアを持っておく|集客力は成功確率に直結する

先にマーケティングや集客の重要性についてお伝えしたが、成功率に直結する集客力のさらなる強化策として、自分のメディアを育てておくことも非常におすすめである。自分の発信力を強化するということだ。
インターネットが普及した現代においてはインフルエンサーと呼ばれる発信力のある個人が一定の影響力を持つが、その力の源泉となっているのが、フォロワー数の多いSNSアカウントや閲覧数の多いブログといった、インフルエンサーが持つメディアである。よって、起業家も自分のSNSやブログなどのメディアを作って育てておけば、集客への活用が見込める。
しつこいようだが、集客力は企業の成功確率に直結する。宣伝の手段はなるべく多く確保しておくべきだ。
12.受託・下請けで稼げるスキルを持っておく|食つなげるだけで続けられる

起業した後は本業で順調に食っていくのが理想だが、そううまくいかないことも多いのが起業の世界である。しかし、起業というゲームはキャッシュが尽きなければ戦い続けることが許される。したがって、本業が不調な時に食つなぐだけの資金を得られる受託や下請けの仕事で稼げるスキルや手段を何かしら持っておくことが大切だ。
具体的なスキルとしてよくあるものを挙げるなら、記事が書けるライターのスキルや、WEBサイトや商品パッケージといったもののデザインスキル、プログラミングスキルといったものが該当する。より単純に言えば、フリーランスとして顧客を獲得して稼げるスキルを持っておくことと同義だと考えていただければよい。
なお、このような特殊スキルがない方は、自転車一台からでも始められるフードデリバリーをはじめとした運送業の経験を持っておくのがおすすめだ。
具体的な手段ややるべきことに関しては後ほど解説する。
13.会社員か学生のうちにクレジットカードを発行しておく

これはよく言われる話だが、クレジットカードの発行は会社を辞める前に絶対にやっておくべきだ。
クレジットカードも住宅ローン等のローンや割賦販売と同様に審査がある。審査基準は会社の考え方や法用件など様々な要素を組み合わせて決められているため、外部の人間が基準を推し量ることは不可能だが、定収入があることは大切な基準の一つであるため、会社員として安定的に給料をもらえる立場の方が有利であることは間違いない。
また、学生のうちは収入が少ないことは当たり前であるほか、多くの場合、両親をはじめとした親権者と生計が同一であり生活基盤が安定している傾向にあることから、(限度額は低くなりがちだが)クレジットカード自体は作りやすいとされている。よって、起業予定の大学生も、持っていないなら今すぐクレジットカードを申し込んだ方が良い(高校生だけは作れないのであきらめるほかないが)。
ちなみに、信販会社に勤めていて与信を行う審査職として働いた経験もある、当サイトの運営者担当者の一人である「じゆとり」に聞いた話だが、審査に堕ちることなく同じように審査に通った人でも、正社員や自営業といった雇用形態や年収をはじめとしたその人のプロフィール(※業界では「属性」と呼ぶ)に応じて設定されるカードの限度額に差が出るということは普通にあるそうだ。よって、会社を辞めて起業する前にクレカは絶対に申し込んでおきたい。
14.必要なローンは会社員のうちに組んでおく|住宅ローンや自動車ローンなど

先に述べたクレジットカードの発行と同じく審査の通りやすさが理由だが、住宅ローンや自動車ローンといった各種ローンも独立する前の段階、すなわち会社員のうちに予め組んでおきたい。
各種ローンにおいても、クレジットカード同様、雇用形態や年収を含む様々な情報から構成されるその人の「属性情報」が審査に利用されるほか、収入が安定しているかという定収入の有無も当然みられることになる。よって、審査の通りやすさや組める金額などは、会社員として安定的に給料を貰っている立場の人の方が大きくなるし、審査にも通りやすい傾向がある。
まことしやかに言われる会社ごとのローンの通りやすさ(例:銀行は厳しい)は否定しないが、全体的な傾向として会社員の方がローンの審査も有利なため、ローンも会社を辞める前に組んでおくのがおすすめだ。
15.ギグワークに登録しておく|一番早くお金が入るが働けるようになるまで時間がかかる

単発や短期の仕事をギグワークといい、代表的な物ではウーバーイーツに代表されるフードデリバリーや、タイミーをはじめとした単発バイトなどが該当する。このようなギグワークは現代社会において合法的に手堅く手っ取り早く金を手に入れる最短の手段であるため、急にお金が必要になったり、いきなり食えなくなる可能性が拭えないものである起業家やフリーランスは必ず登録しておきたい。
ちなみに、お世話になるかもわからないギグワークへの登録を開業する段階で勧める理由は、ギグワークの各種サービスに共通する特徴として、登録を済ませればすぐに稼げるが、登録にある程度の時間や初期投資が発生する傾向が強いためだ。例えば、UberEatsをはじめとしたフードデリバリー各社に配達人として登録した場合、会員登録や本人確認、簡単な研修、バッグをはじめとした配達用具の受け取りなどで、大まかに見積もっても1週間は準備にかかると考えて良い。
必要な時にサクッと稼ぐには前もって登録を済ませておく必要があるため、予めの登録が安心なのだ。
ちなみに、最低限登録しておきたいサービスは以下のとおりである。いずれも、専門的なスキルが無くとも体一つで稼ぐことができる仕事だ。
すぐ働けるギグワーク
- フードデリバリー:Uber Eats・出前館・menu・waltなど
- 単発バイト:タイミー・シェアフル・メルカリハロ・ショットワークス・エリクラなど
16.クラウドソーシングサービスで実績を作っておく|実績がないと仕事の獲得に時間がかかる

資金繰りが厳しい起業家が食いつなぐ手段で、ギグワークより会社経営やフリーランスとしての仕事という側面が強いのが受託である。この受託の仕事を探す手段としてより間口が広い方法が、クラウドワークスをはじめとしたクラウドソーシングのポータルサイトであるため、必ず登録しておきたい。
しかし、ギグワークと違って、登録して満足してはいけないのがクラウドソーシングだ。クラウドソーシングはどのサービスでも実績を積み重ねておかないと仕事が獲得しづらいという共通点がある。よって、起業する前の段階で登録し、実績を積み重ねて仕事を受注しやすくしておくのが理想だ。
17.最悪の事態を想定し退路を確保しておく|失敗した時に会社員に戻れるか?

成功を信じて突き進むことも重要だが、最悪の事態を想定して、退路を確保することも重要な戦略の一つである。起業においても、万が一、事業が失敗した時のことを考えておきたい。
行うべき具体的な検討と準備の内容は、失敗した時に会社員、すなわち雇われて働く立場に戻ることができる目途を立てておくことである。自身のキャリアを活かせる道に戻れることが理想だ。
なお、年齢や経験などの関係で元居た会社の業種や業界に戻れないということもあるだろう。その場合は人手不足で常に求人がある業種に未経験から飛び込むことも選択肢になりうる。一般論で言えば、タクシードライバーなどの各種ドライバー職や、介護職などは慢性的な人手不足で、年齢問わず未経験者を受け入れる土壌も一程度存在している。
開業・会社設立時にやってはいけない失敗と取るべき行動

続けて、実際に起業することが決まったときの初期段階である、開業や会社設立の手続き~事業開始前までにやってはいけない失敗や、やっておくとよいことなどを解説していく。
実際に起業するフェーズに入っているため、ここからの内容は概念的な話より実践的なモノが多く、とっつきやすいはずだ。
1.会社設立は自分でやらない|代行業者で電子定款を使うほうが安い

会社設立の代行業者を調べていると、無料というあからさまに怪しい業者(※後述するがカラクリがあり、実際はそんなこともない)から、何十万円も費用がかかるか、またはそもそも費用がホームページに載っていない業者など、価格帯の幅が大きすぎて相場がわからないという事態に陥ることが多々ある。結果として、「やり方を調べてでも自分でやったほうが安くて安全なのでは?」などと考えがちだ。
しかし、会社設立は自分でやる方が損なので要注意である。理由は、電子定款の使用可否によるコストの差だ。
会社設立時に紙媒体で会社の定款を作る場合、登録印紙代として4万円のコストが発生するが、電子データとして作成する電子定款を選べば、業者への依頼費用の5000円前後と役場に収める手数料は700円程度の交付手数料だけで済む。つまり約3万5000円程度が浮く計算になる。
しかし、電子定款を作るために必要な電子証明書や各種ソフトウェアなどの設備を自分でそろえた場合、10万円前後の設備投資が必要になるため、紙の定款を使う場合よりコストがかかり本末転倒になる。しかし、自分で勉強して紙の定款を使ってしまうと4万円も余計なコストが発生する。こんな踏んだり蹴ったりの制度なので、会社設立代行業者をぜひ活用したい。
会社設立代行業者とは、ここまで解説した電子定款を含む会社設立に必要な書類を代わりに作成してくれる業者である。会社設立の書類作成は、司法書士事務所などの士業の事務所がサービスの一環としてやっているものを使うと数万円以上かかることが珍しくないが、格安の会社設立を謳っている会社設立代行業者を選べば、無料または数千円程度の安価な費用で依頼できる。
普通の会社ならこのような代行業者を使うだけで全く問題なく法人を作ることができるので、代行業者と契約して電子定款を使ったほうがトータルのコストが安い。具体例としては、「マネーフォワードクラウド会社設立」や「freee会社設立」「弥生のかんたん会社設立」などがある(いずれもクラウド会計ソフトの業者だが、強制的にソフトを契約させられるとかはないので心配無用だ)。
また、出資を受けるといった各種事情によりオーダーメイドの定款や書類の作成が必要な場合は、それこそ弁護士のような専門家に徹底的に相談すべきなので、自力で会社設立の手続きを進めるのは論外だ。
以上の理由から、会社設立は自分でやってはいけないと言い切ることができる。
2.税理士の会社設立代行は無料でも使用しない|顧問契約がセットで高くつく

先の「会社設立は代行を使う」という話とセットで必ず憶えておきたいのが、税理士が提供している会社設立代行は無料であっても使わないほうが良いということだ。
このような税理士の会社設立代行の利用料金は無料またはタダ同然の激安価格になっていることが多い。これには当然裏があり、そのカラクリは、代行契約とセットで顧問契約を締結し、自社が依頼企業の顧問弁護士となることで顧問料を得て代行費用を回収し、さらには利益を上げるというものである。よって、「タダより高い物はない」の言葉どおり、割高な顧問料を支払わされる可能性が高い。
誤解しないでいただきたいが、起業するにあたって顧問税理士を雇うことや、税理士に税務やファイナンスの相談をすること自体が悪いわけではない。ただし、税理士の専門はあくまで税務だ。事業を始める段階で特に考慮すべき資金繰りなどのファイナンスを含む事業計画は中小企業診断士、法務には弁護士、知財には弁理士と、そのほかの分野にもそれぞれ専門家がいる。
よって、既に儲かっていて節税を考えるべきフリーランスなどが法人成りする場合はともかく、これから事業を興す人には税理士以上に優先して頼るべき士業がいるはずだ。節税という守りを考えるのは儲かりだした後でもいいし、顧問契約ではなくスポット契約で難しい決算や確定申告だけを安く代行してくれる税理士もいる。したがって、事業資金が限られている場合だけでなく、顧問契約をはじめとした士業の活用は弁護士や中小企業診断士などを優先したい。餅は餅屋だ。
※余談だが、会社設立の代行に生じる書類作成をはじめとした各種作業は、司法書士及び行政書士、または弁護士の独占業務であるため、税理士は彼らに代行費用を支払っていることが多い。
3.印鑑に金をかける必要はない|最安値の素材で十分

成功を夢見ている時は気が大きくなりがちなものだが、そんな夢見る見栄っ張りな起業家の財布を狙っているのが、会社設立の必須アイテムである印鑑の販売業者である。
はっきり言って、印鑑というものは押印できれば素材は何であろうが問題ない。よって、安い素材を選んでネットで買えば、法人印の定番の3点セットである実印、銀行印、角印と、住所を記載したゴム印、(持っていない場合は)代表者の個人の実印と合計5つ購入しても価格は2万円前後に収まるものだ。
しかし、印鑑の通販サイトを見ると、魅力的な高級素材の印鑑がゴロゴロ出てくる。耐久性が最強クラスであるチタンに、印鑑における高級素材の代表格である象牙。そのほかにも、水牛の角、牛角、水晶、琥珀、翡翠、楓、樺などなど、お高い素材の印鑑は盛りだくさんだ。
しかしながら、高い印鑑を買ったからといって経営がうまくいくわけではない。高級印鑑など見栄以外の何物でもない無駄な出費であり、事業への貢献はゼロだ。
よって、印鑑は最安素材である「柘」を選べば十分だ。多少見栄を張ったとしても、柘よりちょっぴりお高い薩摩本柘くらいにとどめておくべきである。
4.決算公告は電子公告を選択する|ホームページへの掲載だけなので格安

株式会社では、上場の有無や資本金額などの条件を問わず、決算後に前年度の決算の内容を公表する決算公告の実施が義務付けられている(※合同会社では義務ではない)。
この決算公告の手段は定款に定めてその方法で行うことになるわけだが、手段として、官報への掲載と新聞広告の使用のほかに、「電子公告」というネット上で公開する方法を選ぶことができる。官報や新聞広告は最低でも数万円以上の多額の掲載費用が掛かるが、電子公告は自社のホームページに載せるだけで条件を満たせて非常にリーズナブルなので、特に理由が無ければ電子公告を選択するとよい。
※決算公告以外にも法定公告と呼ばれる公告の義務が生じるケースが存在するが、法定広告を電子公告で行った場合は、電子公告調査機関という第三者機関に調査を依頼する必要があり費用が掛かる。ただし、決算公告は調査義務が無いため心配は無用だ。
詳細は後述するが、企業のホームページを簡単かつ安価に作成し、維持費も低額に抑える方法はあるので心配は無用である。ちなみに、企業のホームページは社会的信用を高めるためにも必ず作っておくべきであるため、作成を考えていなかった人は検討しよう。
なお、ホームページに決算公告を載せると、自社の業績がネットで知れ渡ってしまうと心配する方もいるだろう。これは、決算公告の掲載ページにnoindexという設定を行うといった方法によって、Google等の検索エンジンで検索してもヒットしないようにして気軽に探せないようにする対策が行える(ホームページを専門知識なしで作れるサービスの多くにこれを設定する機能が用意されている)。
誰にも見られないようにするのは不可能だが、それは官報でも同じことなので、電子公告を使う心配はない。
5.法人口座や屋号付き口座はネット銀行か地元の金融機関を使う

(個人だと意識することは少ないものの)銀行口座の開設時には個人、法人を問わず審査が行われているが、法人口座や屋号付き口座のような事業用の口座は個人口座より開設審査が厳しく時間もかかる。よって、起業したての法人や個人事業主が口座を作る場合は、比較的口座開設がしやすいとされているネット銀行(ネットバンク)や、地域密着の金融機関である地銀や信金、信用組合といった地元の金融機関を使うのがおすすめだ。
ちなみに、特におすすめなのはネット銀行である。理由はインターネットバンキングの使いやすさだ。
地銀や信金などの地域密着型の金融機関では、法人のインターネットバンキングのサービスが有料になっていることが多々あるほか、小さな信用組合や農協ではそもそもインターネットバンキングが無い場合もある。よって、ネット取引しかできないネット銀行のほうが、余計なコストをかけずにインターネットバンキング付きの便利な法人口座や事業用口座を用意しやすい。
また、広く普及しているクラウド会計ソフトに自動で取引を記帳してくれる連携機能が対応している可能性が高いのもネット銀行である。経営効率を高めて本業に注力したいならネット銀行の法人口座や事業用口座はおすすめだ。
6.ホームページは自作する|制作会社やSEOやMEOのコンサルは不要

ホームページ制作はレッドオーシャンな業界であり、調べると大量の業者がヒットする。現在は集客力を高めるSEO対策(※検索エンジン最適化)やMEO対策(マップエンジン最適化=地図アプリなどでの検索対策でローカルSEOとほぼ同義)などのマーケティングもセットで提供する業者も多い。
これらの制作会社はホームページを作った後の維持管理まで任せられるので楽に思えるが、玉石混合の業界なので非常に注意が必要だ。気を付けないとボラれたり、解約するとサイトやドメイン(※URL)が使えなくなったり、多額の移管費用を取られたりする悪質な業者も少なくない。
ここで本題に入るが、現在は簡単にホームページを自作できるサービスが沢山あるため、起業する際はホームページを自作してしまったほうがコスパが良い。これは、実際にWEBマーケティングとホームページ制作の代行業者で働いていた筆者の経験を踏まえての意見だ。
まず、ドメインは同じ文字列のものが二つとして存在しない唯一無二の存在であり、インターネット上の住所のようなものでもあることから資産の一種といえるので、必ず自分で取得し、自分の管理下に置いておくべきである。ちなみに、ドメインの取得はお名前ドットコムといったレジストラと呼ばれるサービスを使えば誰でもできる(※このように自分で契約したドメインを「独自ドメイン」という)。法人名義でも登録や契約を行えるため、会社を設立する場合は法人名義で契約しよう。
また、ホームページの制作に関しては、WixやJimdoみたいなノーコード(=プログラミングなし)で直感的に作成できて、予約やEC(※通販)といった様々な機能も使えるサービスが色々存在しているので、素人でも簡単に作成が可能である。このようなサービスでは無料で使えるドメインも用意されているが、これらは解約すると使えなくなることから、必ず独自ドメインを取得して設定しよう(前述のお名前ドットコムのようなレジストラで契約したドメインが使える)。
なお、少しサイト制作について勉強するつもりがあり、企業ブログを使ったコンテンツマーケティングを行う予定があるのであれば、レンタルサーバーと呼ばれるサブスクのサーバーを契約し、WordPressという世界的に利用されている無料ツールをインストールして使うのもおすすめだ。WordPress用の高機能でハイセンスなデザインテンプレートを販売している業者が多数あるため、これらを購入することでプログラミングなしでホームページを作成し、その中にブログも作って集客に活用することも可能である。
起業するときは浮かれていておしゃれなウェブサイトにお金を出したくなるが、ここまで紹介したWixなどのツールを使っても十分におしゃれなWEBサイトを作成することができるため、お金は他のことに使うべきだ。制作会社を使うのは、仮に今後事業が成長し、ブランディングなどを見据えて超個性的なホームページが必要になったときでいい。
なお、ホームページ制作自体は自分で行うとして、関連する以下の費用自体は外注費を確保しておきたい。
- プロのカメラマンによる写真撮影費用:ホームページは使用する画像素材のクオリティが見栄えに直結しやすい。飲食業など写真の印象が大切な業種ほど外注すべき
- タグの埋め込み費用:低コストから始められるインターネット広告であるリスティング広告やアフィリエイト広告は、準備段階で「計測タグ」といったコードをホームページなどに埋め込む作業が発生しプログラミングの知識が必要なことがある。これらはクラウドソーシングサイトで単発の仕事として募集すればよいが外注費は必要
起業後の経営で回避すべき失敗と取るべき行動

最後に、改行の手続きが終わって事業を開始した後に回避すべき失敗や取ってはいけない行動、とるべき行動を解説していく。当然ながら事業開始後が起業のスタートのため、経営においても注意すべきことは多い。
早々に会社をつぶすことにならないよう、最低限注意すべきことを紹介する。
1.経費を使うことで経営している気になってはいけない

個人的に最も重要だと考えているアドバイスがこれだ。起業すると会社員のように勤務先の会社がお金を出してくれるわけではないため、何をするにもお金がかかる。オフィス、電話、ホームページなどの固定費はもちろん、名刺の発注に広告の作成など発生する出費は多種多様だ。
しかし、このような必要だと思うものにポンポンお金を出していって、経費を使い、領収書をもらうことで経営をしている気になってはいけない。最も重要なのは売上を作って利益を出すことだ。これを間違えないようにしよう。
必要な投資はもちろんやるべきだが、それを含めて経費を使う時はコスパとタイパを徹底的に追求し、同じ商材でも可能な限り安くかつ手間なく済ませることを意識しよう。不要なものはそもそも買わない・導入しないことも重要だ。
2.税理士以外の専門家を優先して雇う|税理士には決算のみを外注できる

「開業・会社設立時にやってはいけない失敗と取るべき行動」の中の「税理士の会社設立代行は無料でも使用しない|顧問契約がセットで高くつく」という項目でも書いたが、起業当初は税務という儲かった後の「守りの行動」より、「攻めの行動」を考えるべきだ。
確かに、法人の場合に年1回は発生する決算を自分でやるのは大変なので決算申告は外注すべきである。しかし、決算申告のみを単発で代行してくれるリーズナブルな税理士が存在するため、一般的に必要そうな顧問税理士を雇う優先順位は低い。
起業当初に考えるべき「攻めの行動」の例を挙げると、資金繰りや資金調達をはじめとしたファイナンスや事業計画の策定(=中小企業診断士の領域)や、法的リスクの対策(=弁護士の領域)、知財の保護(=弁理士の領域)、集客・マーケティング(=コンサルの領域)などがあり、それぞれ専門家がいる。当然、すべての専門家を使わないといけないわけではないが、最初から優先して雇うべき専門家はこちらなので注意しよう。
顧問税理士を雇って節税を考え出すのは、がっぽり儲かってからでも遅くは無い。
3.受託・下請け仕事に時間を割きすぎない|ラットレースから抜け出せなくなる

起業は生き残ることが最優先であるため、運転資金を稼ぐために受託や下請け仕事をすることは全く問題ない。ただし、下請け仕事に時間をはじめとしたリソースを割きすぎると、自社独自の事業を伸ばす時間やお金が無くなってしまい、その月の運転資金を下請け仕事で必死でかき集めて日々を乗り切るラットレースから抜け出せなくなる。
無論、フリーランスのようなクライアントから受託する案件で稼ぐことを当初の目的としている人は問題ない。ただし、自分の事業を継続するための手段として受託をやる人は、受託に時間を割きすぎないよう注意すべきだ。
まとめ|マーケティングに踊らされるな

この記事の総括として、最後にお伝えしたいのが、「起業家志望に群がってくるマーケティングに踊らされるな!」ということ。収益化している営利目的のウェブメディアで起業をネタに記事を書いている自分のことを棚に上げて言うのも滑稽だが、起業を考えるうえで最も重要なことだと思う。
世の中にはお金を使わせようという意図で発信される情報が溢れていて、魑魅魍魎の事業者が我田引水の情報を流し、隙あらば自社商材を売りつけようと画策している。そして、お金を使わせようとする人々にとって最もカモにしやすい顧客の特徴のひとつが、夢を見て、夢を追っている人々だ。
夢を追っている人は、夢想や興奮などによってしばしば周りが見えなくなることが多い。だからうまく焚きつければいい客(=カモ)になる。その中でも、投資の要素がある商材は、それを買うことで自分に利益が生まれるはずだと確信させやすいことから、特に売りつけやすい。
そう、成功を夢見て起業するときは、色々無駄なものを買わされやすいのだ。
この記事でも、「経費を使うことで経営している気になってはいけない」ということを述べたが、実際に起業するならお金を使う部分と使わない部分をよく見極めることが大切だ。「起業するならこれくらい必要だろう」とあれこれ買ったり契約していたら、いらないものにお金を使って気持ちよくなるだけで一向に成果に結びつかないという状況に陥ってしまう。さらに間違えて、「自分ならできる!」という根拠のない自信だけを頼りにまともな計画を持たずに起業していたら、もう目も当てられない。
無計画、勢い、根拠のない自信、虚栄心、現実逃避...etcのような起業家の誰にでもある心の弱さをぐっと抑えて、計画的に泥臭くやっていきましょう!
